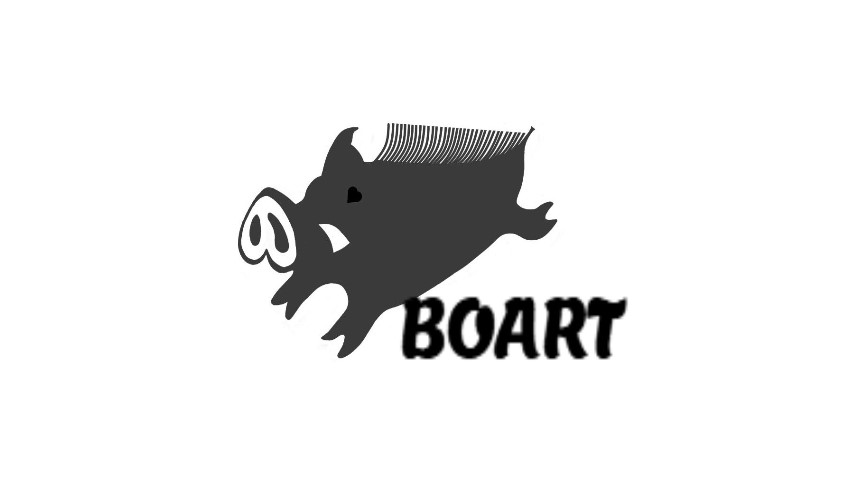画像をクリックすると拡大されます。また作品名をクリックするとハンドメイドマーケット「minne」、あるいはハンドメイドマーケットプレイス「Creema」に移動予定。
Click on the image to enlarge it. Also, click on the name of the work to go to the handmade market “minne” or the handmade marketplace “Creema”.

色と形が交錯するこの猪は、単なる動物ではなく、季節の境界を駆け抜ける象徴的存在。 秋の始まりに、私たちの内なる衝動と、土地に宿る記憶が交差する瞬間を捉えている。

草のざわめきに耳を澄ませるように、猪は立つ。 その姿は、季節の境目に現れる気配そのもの。

野生の猪が立つのは、ただの草原ではない。風が通り抜け、季節が語りかける場所。 その毛並みは、土と光の記憶をまとい、耳は遠くの気配を聴いている。本作は、自然の中に潜む「存在の確かさ」と「孤独の美しさ」を描いています。 観る者の心に、静かな問いを投げかけるように。

静寂の隅に、猪がひっそりと顔を覗かせる。人の棲み処と野生の気配が交差する瞬間——それは、自然との共鳴であり、忘れられた記憶の呼び声でもある。この作品は、「棲む」という行為の詩的側面を探ると同時に、野生との共存、季節との対話を描いている。落葉の絨毯は、過ぎ去った時間の記憶であり、これから訪れる沈黙の予兆でもある。猪のまなざしは、境界を越えてこちらを見つめる、もうひとつの「家」の存在かもしれない。

猪は山を離れ海をも駆ける。 その姿は、記憶の深層から跳ね上がる創造の原型。 太陽は、過去と未来の狭間に灯る意志の象徴。本作は、まだ語られていない物語の使者として、 海上に現れることで、私たちの内なる変容を問いかける。

暗雲垂れる秋の野を、猪がひとすじに駆け抜ける。 「猪」は、古来より境界を越える存在として描かれてきた。 この作品は、自然と人、静と動、過去と未来の狭間に立つ、 一頭の猪の詩的な肖像。

昼の街路に、ひとつの影が渡る。 雨上がりの光が、建物の色彩を滲ませ、路面に揺れる。 都市の秩序の中に、野性が一瞬だけ姿を見せる。本作品は、日常の明るさの中に潜む異質な気配を描き出す。

夢が色を纏い、花を咲かせる。 それは、静かな衝動のかたち。

この眼差しは、山を駆ける記憶か、それとも霧の中に潜む問いか。猪の顔の一部を切り取ることで、見る者に「部分から全体」を想像させる余白を残す。背景の色彩は、山の気配と季節の揺らぎを抽象的に表現。 これは、静けさの中に潜む力を描いたひとつの肖像。

その眼差しは、獣の本能と土地の記憶を宿しながら、 人と自然の境界に立つ存在として、静かに問いかける。 この作品は、季節の移ろいと命の気配を描きながら、 「立つこと」の意味を私たちに投げかける。 — それは、抵抗か、受容か、それとも祈りか。

草のざわめきに耳を澄ませると、そこに潜む命の気配が立ち上がる。 風を裂き、季節の境を越え、土地の記憶を呼び起こす。 野生と静寂が交差する瞬間を描く。

森の奥、季節の境目に現れる猪。その姿は、土と風の記憶を纏いながら、光の粒子と交錯する。 本作は、山間に響く野生の鼓動を、印象派的な筆致で捉えた。 背景に広がる緑と黄の揺らぎは、「小さな季節」の気配と猪の存在が自然のリズムと共鳴していることを示す。 猪が歩むことで目覚める土地の記憶と、観る者の内側に響く生命の律動を重ね合わせた。

光と闇が交錯する裂け目に、猪は姿を現す。 本作は、季節の移ろいと地域の記憶、そして内なる衝動を重ね合わせ、 猪という象徴を通じて「変容の瞬間」を可視化する試みである。

森の奥、黄葉の敷かれた径に佇む幼き猪。 その鼻先は、まだ知らぬ季節の匂いを探り、 その眼差しは、光の粒を追いかける。本作は、「猪」という象徴が持つ野性と無垢、 そして地域に根ざす命の循環を表現した。観る者の記憶の森に、 ひとつの光が差し込むことを願って。

咲き乱れる色彩の中、 黒きモノは立つ。 静かなる異物として。 それは、季節の裂け目に立つ。 土地と命の境界に、 ひとつの神性が宿る。

「猪目(いのめ)」は、災いを祓い、心を守るかたち。本作は、その猪目に、猪という生命の象徴を重ねることで、衝動と祈り、突進と沈黙のあいだにある「心のかたち」を描き出す。

この作品に描かれたうり坊は、単なる動物ではなく、森の奥に芽吹く「再生の予兆」としての存在。縞模様は自然との境界を曖昧にし、無垢な感覚と直感の象徴。 地域文化においては、うり坊は里山の記憶と神性の芽吹きを担い、命の循環と精神的風景を静かに語りかける。 本作は、季節の境界に立つ命の鼓動を詩的に描き出している。

草の匂い、雲の影、風が通り過ぎたあとに残る、静かな午後の光。この風景は、季節の移ろいと人の営みが交差する場所。 人の暮らしと自然が、互いに干渉せず、 ただ同じ空の下にあるということ。 その距離感が、懐かしさと未来への余白を生む。

咆哮は言葉なき対話であり、山と空、緑と影が交錯するこの風景は、自然の中に潜む感情の震えを映し出す。 本作品は、動物の本能と風景の静けさを対比させることで、私たち自身の内なる葛藤や変容の予兆を描き出す。

暗がりに浮かぶ、うり坊の姿。 その毛並みは、秋の光に染まる稲穂のよう。この作品は、野生の命が持つ「柔らかさ」と「孤独」を描いています。 背景に広がる深い色彩は、里山の夕暮れや、記憶の奥に沈む風景を想起させ、見る者の内側に眠る感情をそっと揺り起こします。

眼差しは、季節の境界を見つめ、波の記憶を聴いている。 牙は時間を裂き、空の色は魂の変容を映す。

濡れた舗道に灯りが滲む都市の夜。 人の営みが眠りに向かう頃、 一頭の猪が静かに通りを横切る。それは、忘れられた野性の記憶か、 都市の奥底に潜む魂の象徴か。

暖色に染まる地面を踏みしめ、風土の記憶を静かに呼び起こす。 猪の姿は、私たちの内なる移動と、土地との対話を映す鏡である。